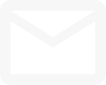人間も生き物である以上、食べることは生きるために欠かせません。しかし、昨年の日本の食料自給率はわずか38%にとどまり、約6割の食料を海外からの輸入に依存しているのが現状です。さらに、農業従事者の平均年齢は69歳と高齢化が深刻に進行しており、このままでは食料自給率を向上させるのは容易ではないと考えられます。
一方、他の先進国では、食料の確保を国家の安全保障と直結させ、食料自給率100%を目指す取り組みがなされています。これは、仮に戦争や国際情勢の悪化によって輸出入が途絶えた場合でも、自国で生産した食料で国民を賄える体制を整えておくことが不可欠だと認識されているためです。
日本においては、主食である米の生産と消費を安定させることが、食料自給率向上に向けた第一歩となります。近年、米の消費量は減少傾向にありますが、米粉を使ったパンやスイーツといった新たな需要の創出も進められています。また、若い世代の農業参入を促す支援策や、IT技術を活用したスマート農業の導入も、生産力維持と効率化に向けた重要な取り組みです。
さらに、米に限らず、野菜、果物、畜産物といった幅広い分野で国産化を進めることが求められています。都市部では小規模な市民農園や家庭菜園の普及も進み、消費者自身が食料生産に関わる意識を高める動きも見られます。加えて、食育活動を通じて「食べるものは自分たちで支える」という考え方を広げていくことも重要です。
これからの日本において、食料の確保は単なる経済問題にとどまらず、国民の命と暮らしを守る安全保障の要となります。私たち一人ひとりが国産食材を積極的に選び、農業や食料生産を支える行動を意識することが、未来にわたって不可欠なことだと考えています。よんくるでは、「食」という面からもこれから考えていかなくては、と、思います。