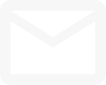9月と言えば、防災ですね。最近では酷暑も災害のカテゴリに入るのかもしれません。そこで、今回は地域防災について考えてみたいと思います。
徳島は、吉野川下流域で液状化による家屋倒壊も心配されています。南海トラフ巨大地震が起きれば、甚大に被害が出るでしょう。その時は「近助」の仕組みが必要です。家族が遠くにいる場合、近隣同士で助け合うしかありません。
災害が起きた直後は、行政や自衛隊の支援が届くまでに時間がかかります。電話やインターネットも繋がらず、家族の安否を確認することすら難しい状況になるかもしれません。そんなときに頼れるのは、やはり身近に住む人たちの存在です。普段から顔を合わせ、挨拶を交わしている隣人との関係は、いざという時にお互いの命を守る大きな力となります。
地域での防災は、特別な活動ばかりではありません。日常的に交わすちょっとした会話や、近所の人の生活リズムを知っておくことが、災害時には安否確認や避難支援につながります。「あの家には高齢の方が一人で暮らしている」「こちらの家には小さな子どもがいる」――そうした情報を知っているだけで、助け合いの行動が取りやすくなるのです。
また、自治会や町内会での取り組みも大切です。避難訓練や安否確認の練習、防災倉庫の点検といった活動は、参加してみると意外に身近で現実的な内容です。こうした取り組みを通して、「自分たちの地域を自分たちで守る」という意識が育まれていきます。
自助だけでは限界があり、公助もすぐには届かない。だからこそ、近隣で助け合う「近助」が必要なのです。防災月間であるこの9月を機に、地域とのつながりを改めて意識し、普段から少しずつ関係を深めていくこと。それが、私たちにできる一番身近な防災の第一歩なのかもしれません。